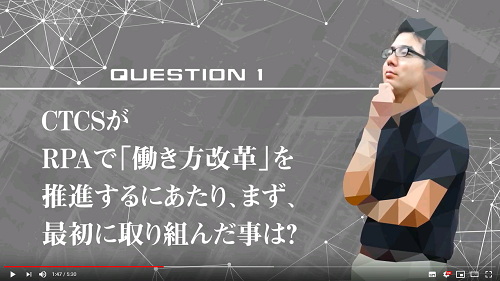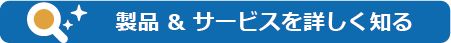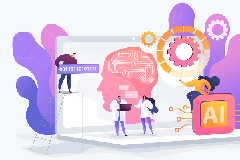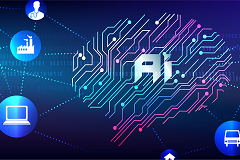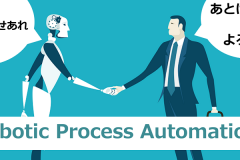AI・RPA|知る×学ぶ
働き方改革とRPA|導入で直面する課題と解決方法とは
働き方改革の重要テーマの1つである長時間労働の是正。これを実現するためには、業務の生産性向上が欠かせません。
そのための手段として注目されているのがRPAの活用です。
それではRPAによる業務改革を成功させるには、どのようなアプローチを行うべきなのでしょうか。
本記事では、働き方改革の事例を取り上げ、RPAの選定や推進体制について解説します。
▼ 目次
1. 働き方改革の推進で見えてきた課題
2. 業務効率化の手段として注目されるRPA
3. 事例に見る、働き方改革におけるRPA活用
4. RPAによって働き方改革を成功させるためのポイント
1. 働き方改革の推進で見えてきた課題
政府の旗振りのもと、すでに多くの企業で進められている働き方改革への取り組み。
長時間労働による私生活の圧迫や、過労死といった問題を解消する上で、このような動きは不可避だといえるでしょう。
また出産や介護に伴う離職を防止し、働き手を確保し続けるためにも、限られた時間で働ける制度を創り出すことが求められています。しかしその道程には、大きなハードルが横たわっています。
例えば、残業を減らすために定時退社を促したとしましょう。
無駄な会議を減らす、ITツールを活用して直行直帰を可能にする、といった対応で、ある程度までは業務時間を短縮できるかもしれません。しかし実際に行うべき業務量が以前に比べて減っていなければ、その効果も限定的になってしまいます。
定時退社のルールを守るため、その日の仕事が終わらないうちに帰宅してしまえば、残った仕事が翌日に持ち越され、よりハードな状況で仕事をすることになってしまうでしょう。
このような状況を放置したまま働き方改革を進めてしまえば、結局はサービス残業が増えてしまい、本来の目的を達成できなくなります。
長時間労働を是正するには、まず業務のあり方を根本から見直し、必要な業務とそうでない業務を仕訳しなければなりません。
そして必要な業務に関しても、徹底した効率化を推進し、業務量を削減していく必要があるのです。
2. 業務効率化の手段として注目されるRPA
働き方を改革するための手段として注目されているのがRPAの活用です。
RPAとは「Robotic Process Automation」の略であり、コンピューターを利用した業務の自動化や効率化を、ソフトウェアロボットによって実現していくという取り組みを意味します。
(RPAの基礎解説については、下記よりご覧いただけます。)
現在でもホワイトカラーの業務の中には、データ入力などの単純作業がかなりの部分を占めています。これをソフトウェアロボットで代替させることができれば、人間が行うべき作業が削減され、業務時間も短縮できると期待されているのです。
また最近のRPAは、かなり複雑な作業も自動化できるようになっています。このようなRPAツールを活用することで、幅広いオフィスワークの生産性を高めることが可能になります。
すでにRPAを活用した自動化によって、業務効率を高めることに成功した事例も数多く登場しています。
その一例としてここでは、CTCシステムマネジメント株式会社(CTCS)による「システム運用の自動化」を紹介しましょう。
3. 事例に見る、働き方改革におけるRPA活用
CTCSは顧客のITシステムを最適化するサービス&ソリューションを提供する企業であり、システム運用もサービスメニューに含まれています。つまりシステム運用は同社にとって事業の柱であり、これを自動化・効率化できれば、働き方改革に大きな貢献を果たせることになります。
しかしそこには、乗り越えるべきハードルが存在していました。
最近のネットワークは多様化しており、独自アプリケーションを使った作業も数多く存在します。そして設定変更やアプリケーション改修を行った際には、様々な環境でのテストを網羅的に行わなければなりません。これらを自動化していくには、RPAツールをどのようにして各業務に落とし込んでいくのか、という検討を行う必要があったのです。
それではなぜCTCSは、このハードルを乗り越えることを決意したのでしょうか。CTCSでRPAによる働き方改革のプロジェクトリーダーを務める坂西氏に伺ってみました。
CTCSの坂西氏は次の通りに答えます。「当初は業務の見直しから着手したのですが、自動化や効率化のために業務フローを大きく変更するという従来型のアプローチでは、業務改革に1~2年の時間が必要になることがわかりました。これに対してRPAによる自動化は、業務フローを変える必要がないため、短期間で実現できる点が大きな魅力です。RPAはツールの縛りに業務フローを合わせる必要がありません。RPAの登場によって、業務改革のもう1つの考え方が提示されたと言えると思います。」
動画 1. RPAで「働き方改革」を推進するにあたり、最初に取組んだ事
4. RPAによって働き方改革を成功させるためのポイント
RPAの導入を成功させるポイントは大きく2つあります。
4-1. RPAツールの選定
RPAツールを選定するポイントは、業務内容や企業文化、社内ルールによって大きく左右されます。
そこで一般的なオフィスワークの自動化を例に、RPAツールを選択するためのコツについて、坂西氏に伺いました。
- ツールの特徴は千差万別なので簡単ではありませんが、まずは様々なツールを触ってみる
- 小規模な取り組みを行った上でその効果を評価し、本格的に導入するか否かを決める
- ベンダーの言うことを鵜呑みにせず、当社でも複数のツールを対象に、懐疑的な姿勢で選定を進める
CTCSにおいても様々なRPAツールを試しました。
最終的にツール選定に重要視したポイントは、監視ツールやその他のツールとの親和性だったと坂西氏は語ります。
4-2. RPAを定着化するための推進体制作り
RPA導入の成否を分ける大きな要因に推進体制があります。
- どの部門がRPAの導入を推進するのか
- 推進チームにどのような人材がいるのか
そこで、RPAを利用する部門が主体となって推進する場合、どの様な体制でRPAの推進に臨むべきか、坂西氏に伺ってみました。
- 将来に発生するRPAの管理負担を配慮して、早い段階でIT部門に関与してもらうと良い
- プログラミングの知識を持つ人材を体制に含める
RPAは『ノンプログラミング』です。従って、プログラミング言語の知識は不要です。
しかし、処理フローを検討する上では、あらゆるエラーケースを想定できる思考能力が重要になります。
よって、プログラム上のロジックを理解しておくことで、複雑な処理が必要になったときに適切に対応しやすいからです。
CTCSにおいてRPAを導入するにあたっては、様々なスキルを持つ人材から構成される5名の推進チームを編成したと坂西氏は語ります。
上記に挙げた点以外にも、下記のポイントもRPA定着化の成功への近道になると坂西氏は語ります。
- 事前に業務内容の手順書を作成しておく
- RPAに適した業務とそうでない業務を見極めカスタマイズや開発を最小化する
- 上層部と推進チームとの間で効果への期待値に関する共通認識を持つ
まとめ
本記事で述べたことをまとめると、以下のようになります。
- 働き方改革の重要テーマの1つである長時間労働を是正するには、業務の生産性向上(業務改革)が不可欠。そのために注目されているのがRPAの活用。
- 業務改革では業務フローの見直しを行うのが従来の一般的な方法だったが、RPAであれば業務フローを変更することなく自動化を行える。
- ただしこれを成功させるには、注意すべきポイントもある。ツールをどう選択するか、推進をどの部門が担当するのか、推進チームにどのような人材を配置するのかなどについて、配慮しながら進めていくといい。
このようにRPA活用への適切なアプローチを行うことで、働き方改革を短期間で加速できる可能性があります。さらに詳細な情報は以下URLに掲載していますので、こちらもぜひご参照ください。